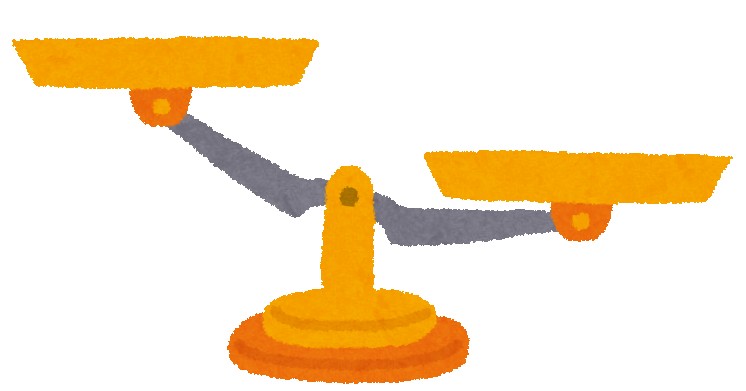競馬のマネーフロー
先日、福島競馬場から駅までのタクシー内で運転手氏と会話していた時のこと。彼は、馬券の払い戻しとは控除率を引いた配当額であると知らず、私の指摘が初耳だったようで、かなり驚いていました。
競馬ライターの水上学です。今回も「水上のニュースレター」をお読みくださりありがとうございます。メルマガ未登録の方は、ぜひ無料での配信登録をお願い致します。
この運転手氏は、馬券も同僚たちがダービーや有馬記念の馬券購入で盛り上がっている際に、便乗して少し買ったことがある程度、との話でほぼ無関心層。なおこの運転手氏は、払戻金額が大きいいわゆる「大穴馬券」が出ると、JRAが損をするのだとも思っていたそうです。
当原稿は一般公開のため、読者の皆さまは競馬に詳しい方ばかりではないので、もしかするとこの運転手氏と同じように思っていたケースもあるかもしれません。我々のような競馬関係者やファンを自称する方なら当然のことと認識していても、競馬を知らない人たちにとっては彼のように初耳となる事象は少なくないのでしょう。そこで今回は、馬券の売り上げが国とどのように関わっているのか、その流れを紹介してみることにします。
もちろん競馬ファンにとってはご存じのことばかりかもしれませんが、改めて確認の意味で最後までお読みくださると嬉しく思います。
◆売り上げの全てがJRAに入るのではない
馬券の売り上げ、それは最低購入単位100円の馬券がどれだけ買われたか、その総計となります。近年はおおよそ年間で3兆から3兆2000億円を計上していますが、その内の75%が払戻金に回されています。つまり、払戻金は最初からその分を別に分けているので、高額配当になっても、どこが損をするということはないわけです。
残りの25%のうち、10%分が国庫に入ります。これは第1国庫納付金と呼ばれます。第1があるからには第2もあるわけですが、これは後ほど出てきます。
そして最終的に残った全体の15%。これがJRAに入ります。年間4000億円から5000億円の間といったところになりますね。このお金を、さらに次のように振り分けることになります。
① 競馬事業費→いわゆる「ランニングコスト」です。光熱、水道、清掃費用や馬場整備事業、設備運営費など、またCMなどに代表される広報活動費などもここに含まれます。
② 業務管理費→大まかにいうと職員の給与などです。
③ 競走事業費→レースの賞金が中心となります。
先ほどの15%から、以上3つの費用を引いた結果が黒字になれば、それがJRAの収益となります。これが大体年間600億から800億円といったところ。
ただ、この黒字収益にもさらに納付義務が生じます。その50%を、先ほど予告した第2国庫納付金として国へ納め、残り50%が畜産事業や競馬振興のために使われることとなります(特別振興資金といいます)。
年に何度か「今日は払い戻しに5%上乗せします!」という、一見嬉しいような、でも冷静に考えると、当たらなかったら何の恩恵もない?サービスデーがありますが、この上乗せ分もここから捻出されます。
なお、馬に限らずですが、家畜伝染病の防疫研究費、ワクチン代の補助、一般的な農畜産動植物の品種改良のための研究費も出されていて、地味ながら社会貢献度は大きなものがあります。
つまりこれこそが公営ギャンブルのアイデンティティとでもいうべきものであり、これだけの「上がり」を国に納めているからこそ、大手を振って大衆が楽しめることになります。昨今社会問題となっているオンラインカジノは、国に納める金額がない=非公認の闇ギャンブルであるので取り締まりの対象となっているわけです。
◆払い戻し率と控除率
馬券の種類により幅はありますが、JRAの場合は最初から約25%前後の控除を行っていることは、ここまでの話でお分かりいただけたと思います。
ということは、馬券を購入した時点で、100円で買ったあなたの馬券の価値は75円に下がっているということを意味します。だから馬券が的中して払戻金を受け取る場合にも、勝った時の100円に対する倍率ではなく、75円に対する配当倍率でオッズが出ているわけなのです。
控除率25%なら当然払い戻し率は75%になります。控除率と払い戻し率は対称の関係にあります。
そして券種ごとに払い戻し率は微妙に異なります。
単勝と複勝→80%
枠連・馬連・ワイド→77.5%
馬単・3連複→75%
3連単→72.5%
WIN5→70%
とこのように多少の幅はありますが、平均すると75%と考えていいでしょう。配当が高めの券種ほど払い戻し率は低くなります。
また公営ギャンブルの種類によっても払い戻し率は異なります。競輪とボートレースは75%、バイクレースは70%、宝くじが最も低くて46%なのです。
そして、日本競馬の払い戻し率を競馬の主要国と比較してみると、イギリス77%、フランス85%、アメリカ79%、オーストラリア86%、香港84%となっていて、これらの国との比較では、日本の払い戻し率は最も低いことになります。ただ、年間売り上げが日本とは比べ物にならないくらい低いので、払い戻し率を下げてしまうと深刻な客離れに繋がるための設定であり、とくに気前よくサービスしているわけではないとも考えられます。
◆払戻金への課税問題
数年に一度、新聞やテレビのニュースを賑わせるネタとして、馬券で高額の配当を得たのに申告せず、脱税の疑いで書類送検されたとか、追徴課税されたとかの報道をご覧になった方も多いでしょう。今度は配当と税金の関係について見てみることにします。
2007年から09年にかけての3年間、インターネットで馬券を購入した会社員が、28億7000万円の購入に対し30億1000万円の払い戻しを得ていたのに申告せず、大阪国税局から摘発された「卍事件」がありました(卍はこの会社員のWebネームです)。国税局は、この30億1000万円の払い戻し全額に対し、一時所得として5億7000万円の課税を要求。
これに対し、卍氏は馬券購入代金を引いた純利益である1億4000万円分への課税を主張し大阪地裁へ訴えを起こしました。最高裁まで争われたこの裁判、結局卍氏の主張が通り、利益となった分への課税額5000万円の支払い命令で決着をみたのです(なお卍氏の脱税への罪は成立、執行猶予付きの有罪判決となりました)。
この主張が最高裁で通った理由として「原告は継続して多額の馬券を購入しており、事業として認められ、一時所得ではなく雑所得として扱うのが妥当」という判断がありました。以後、馬券の脱税摘発が起きるたびに、これが判例となって、年間の購入金額と継続性が焦点となり、同様に雑所得として利益にのみ課税されるケースが大半を占めています。
なお一時所得とみなされた場合は、当たり馬券そのものに投資した金額しか、経費として認められません(例えば全体で10000円投資して、3連単100万円の配当を100円分的中した場合、経費と見做されるのは10000円ではなくて100円のみになります)。
よく問題となるのは、配当金への課税がそもそも二重課税に当たるのではないか、ということ。専門家の間でも見解が分かれているので、筆者のような法律の素人が何を語ることもできません。ただ、二重課税にならないとする現在の公式見解としては、先ほどから説明してきた25%の天引きはあくまで控除であって所得税とは異なるもので、払い戻した時点で所得となる金額への課税はしていないというのが基本的な了解点となっているようです。
もっとも、払い戻しについてはその立証ができるWeb上での購入しかこれまでのところは摘発されていませんし、また一時所得にしても年間で50万円以上の払い戻しを受けた場合だけが対象となります。この50万という額をもっと上げていいのではないかという気は個人的にしますが、慎ましい庶民がささやかに楽しむ分には、何のお咎めもなく楽しむことができるはずなので、あまり気にする必要はなさそうですね。
すでに登録済みの方は こちら