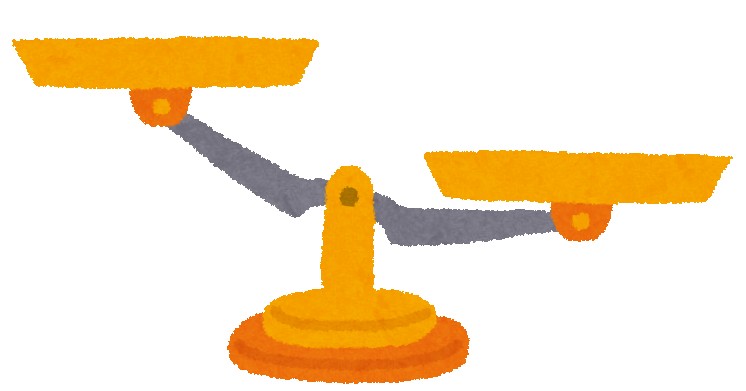「競馬の豊かさを知る・お薦めbookガイド7選」
しかし情報ではなく知識を得るためには書物にあたるのが一番・・・と考えるのはもう「昭和脳」なのでしょうか?書物から得たものは、消費されずに自らの内に蓄積していくような感じがするのは、筆者だけなのでしょうか?
競馬ライターの水上学です。今回も「水上のニュースレター」をご購読くださりありがとうございます。メルマガ未登録の方は、ぜひ無料での配信登録をお願い致します。
なおコメント欄を開放しております。みなさまに伺いたいテーマを文末に記しておりますので、今回も最後までお読みくださると幸いです。
◆本題の前に雑感を
筆者には心理学や行動認識論の専門知識は無いので、偉そうなことは書けませんが、全体を一望できるという物理的な視野の広さ(狭さ?)、照度と眼の関係、そしてよく言われることではありますが、書物の重さやページを繰るといった触覚との連動などにより、本から得られるものは記憶に残り易いという実感があります。
もっとも、それは物心ついてから成人するまで紙媒体を中心に情報や知識を得ていた世代だからかもしれませんが、いわゆるインパクトの強さ、インデックスとしての記憶はデジタル媒体から受ける方が残っている気がするものの、理論的な展開や周辺情報については、紙媒体から受ける方が頭に入ってくる気がするのです(あくまで個人的な感覚です)。
ですから、今のデジタルメディア中心の生活をしている時代においては、たまには能動的に紙媒体に触れて、見落としていたものや気付かなかったことを掬い上げるのが必要なのではないかと考えています。
思えば競馬においても、オグリキャップが火付け役となっての1990年代の大ブーム当時は、まだデジタル媒体が一般には無かったので、書籍、雑誌を介してさまざまな知識の敷衍が行われていました。そこには馬券本の類も当然ありましたが、名馬たちのドキュメント、競馬を支える人たちの日常、競馬の歴史や雑学、さらに以前にも少し書きましたが、ウマ娘の元祖ともいうべき競馬コミックの秀作の数々、今は死語かもしれませんが競馬ミニコミも百花繚乱でした。予想や馬券ではなく、競馬の根っこの部分から入ってくる人の方がむしろ多かった(個人的にみて)ので、そうした人たちには、じわじわと火が通っていくような感じでいつしか競馬が身体に染みつき、生涯の「趣味」として、何十年も付き合う羽目になっていったわけです。
一方で競馬はギャンブルであり、馬券が当たった・外れたという面も重要ではあると思いますが、これだけだと、ハズレが続けば興味が失せるし、あるいは逆に取り返すことにのみ血道を上げてしまうので、負けが込んで馬券を買えない境遇に陥った場合には退場せざるを得なくなります。ところが、そうではない側面から競馬に入っていった人たちは、ギャンブルへの関り方をうまくコントロールできているケースが多いですし(もちろん例外はありますが)、また何らかの理由で馬券が買えなくなったとしても、競馬観戦は継続して、好きな馬や騎手を見つけて応援し続けているというような例を、筆者の身近にも見ることができます。
ただ文化としての競馬は、その後傍流に追いやられることになります。2000年代以降はそうしたテーマの本よりも「こうすれば馬券が当たる」というようなノウハウに競馬本の比重が移っていきます。それは読者からの需要でもありました。競馬ファンが馬券ファンになっていく過程で、もっと当てたい、当てるにはどうしたらいいのか、という声が主流になったわけです。新しい売れ筋を探して、時代の要求に合わせていくのは商業出版として当然のこと。もちろん文化的側面からの本も継続して出てはいましたが、出版社側から書き手にそれを求めてくることはレアケース。よほど優れた企画や切り口、あるいは著者のネームバリューや職種の特殊性などをフックにしないと出せないことも多くなっています(いるように思えます)。
かくいう筆者もいわゆる「馬券本」ではない本は1冊しか出したことはないのですが(汗)、あまりにも予想へ偏り過ぎて「馬券に直結した知識を求めることこそが正義」だと、出版サイドが思い込んでいるような気がしたことも、一度や二度ではありません。
話は逸れてしまいましたが、前半に敢えて筆者が考える競馬本の意義について述べてみました。ただのノスタルジーと受け止められても仕方がないのですが、多少なりとも共感された方なら、これから紹介する書物を楽しめることは間違いないです。
職業によって余暇が取れる時期は異なるとは思いますが、年末から年始にかけては、旅行や帰省するという方、自宅で寝正月という方、共に自分の裁量で使える時間が普段よりは多いのは確かでしょう。移動中の乗り物内、ホテルや実家のソファの上などで、スマホではなく本を手にする時間を少しでも作るには、絶好のチャンスではないでしょうか(荷物になる?)。
今回は、私が実際に読んだ本の中から、胸を張って推薦できる競馬本を7冊、僭越ながら紹介することにします。競馬や馬に関する周辺知識や歴史、文化的側面に雑学など、こういう機会でもないとなかなか摂取できない滋養ともいうべき要素を持った7冊です。
選択基準は「直接の予想本ではないこと」「現在入手可能であること」の2点。ただ最後のものはやや入手困難かもしれませんが、図書館なら大丈夫だと思います。
なお取り上げた順番は推薦度合いの強弱を表すものではなく、まったくのランダムです。カッコ内は敬称略で著者、出版社です。本の内容についてはネタバレになるので詳しくは書きません。
◆お薦め競馬本ガイド7選
◎「サラブレッドに心はあるか」(楠瀬良・中公新書ラフレ)
ウマ博士として数々の名著を送り出した、元JRA獣医で競走馬総合研究所主任研究役を務められていた楠瀬氏。専門は馬の心理学や行動学ですが、なんといってもその分かり易さが素晴らしい。学術的な内容をとにかく平易に、読んで楽しくなるような筆致で書いてくださっています。武豊騎手との対談で、レース中の馬の反応と馬学を結び付けておられる部分は特に読み応えがあります。

なお他の楠瀬氏の著作には、現在入手困難なものや中古本市場にしかないものもありますが、見かけたら即買いでいいくらいです。「サラブレッドはゴール板を知っているか」は特におすすめです。
◎「生物学・遺伝学に基づくサラブレッドの血統入門」(堀田茂・星海社新書)

「科学に普段触れない人たちと、専門家との橋渡しこそが使命」とおっしゃる堀田さん。専門は遺伝学ですが、競馬への造詣が深く、サラブレッドの血統を生物学、遺伝学観点から探求なさっています。世界の国際GⅠ競走勝利馬を網羅した母系樹形図の作成をライフワークにされていて、筆者もたくさん学ばせていただいています。競馬における母性遺伝の重要性を、実際の名馬やレースに即してとても分かりやすく展開されています。
◎「覚えておきたい日本の牝系100」(平出貴昭・競馬道オンライン新書)

母性遺伝の話が出たところで、この本もぜひ紹介したい。サラブレッド血統センターの平出さんの著作です。種牡馬偏重の競馬界において、いかに牝系が重要か、牝系図の紹介に留まらず丹念な分析を加えた力作です。これは競馬初心者というよりも、血統に興味がある方、中級以上のファンの方が楽しめると思います。
◎「競馬の経済学」(渡辺隆裕監修・カンゼン)

東京都立大学・経済経営学部教授で、ゲーム理論の専門家である渡辺さんが監修した、競馬をあらゆる角度から、とにかく経済的側面だけで換算してみた異色の本です。著述というよりデータ本といったほうがふさわしいですが、本当に面白い。NHKで放送している「お金発見・突撃カネオくん」(知らない方はごめんなさい)の競馬版というニュアンスで、好奇心をくすぐられる一冊です。
◎「競馬の世界史~サラブレッド誕生から21世紀の凱旋門賞まで」(本村凌二・中公新書)

古代ローマ史研究の大家にして、競馬界の賢人としても知られる本村東大名誉教授の著作です。本村先生はJRA馬事文化賞も受賞されていて、競馬のみならず馬を世界史的視点からとらえ、人間との数千年にも及ぶ関りを俯瞰されてきた方です。数年前まで、凱旋門賞を毎年のように現地で観戦されており、欧州競馬に関する造詣では日本で唯一無二の存在です。なお筆者は酒席を2,3度ですが共にする機会があり、その博識に圧倒されました。
◎「競馬どんぶり」(浅田次郎・幻冬舎アウトロー文庫)

説明不要、馬主でもある浅田次郎先生の競馬エッセイ。世を忍ぶ単なる一ファンとしてのお姿を、時折東京競馬場のスタンドでお見掛けします。ドロドロの競馬オヤジ(失礼)としての日常、勝負事におけるゲン担ぎや馬券の失敗談など、ニヤリと笑えるエピソードがたくさん詰まっています。
◎寺山修司の競馬ノンフィクション集
「馬敗れて草原あり」「競馬への望郷」その他(角川文庫、河出文庫、新書館など)

そして、最後にはやはりこれを挙げずにはおれません。70年代から80年代にかけて、多くの若者を競馬の沼に引きずり込んだバイブルのような著作群。以前は著作集がシリーズで何度も各社から再販されていたのですが、今は絶版しているようで、Amazonなどで出回っているものを買うしかないようです。見かけたらぜひ・・・。競馬とは何か、なぜ人は競馬に惹かれるのか。「競馬が人生の比喩なのではない、人生が競馬の比喩なのだ」は永遠の名言です。
**********************************
今回も最後までお読み下さりありがとうございました。大半の本にkindle版がありますが、今回の趣旨からしますと、できれば本の形で手にされることをお勧めします(笑)。
なおよろしければ「私がお薦めする競馬本・この一冊」というテーマで、気が向いたら書き込んでみてください。楽しみにしております。
◆お知らせです。
*私が主宰しているWeb競馬サロン「水上学と絶叫する会」では随時、会員を募集しています。
詳しくは
のリンク、あるいはおすすめからアクセスをよろしくお願い致します。
*毎週の競馬予想は上記サロンの他、競馬ラボ、競馬JAPANで検索してみてください。
*YouTubeチャンネル「水上学の競馬大学」も随時更新しております。関心のある方は覗いてみてください。
*「月刊・競馬の天才」連載中です。最新号が13日に発売されました。
すでに登録済みの方は こちら